
 建設会社が、外国人技能実習生を雇用するには、建設業許可(金看板)が必要になりました。詳細はこちらをご覧ください。
建設会社が、外国人技能実習生を雇用するには、建設業許可(金看板)が必要になりました。詳細はこちらをご覧ください。
建設業界の外国人雇用
建設業界も他業界と同じように、深刻な人手不足に悩んでいます。
日本では、原則として外国人の単純労働は認められておりませんが、人手不足に悩む建設業界も外国人の労働者に頼らなければ、やってゆけないのが現状です。
そこで例外として、外国人の雇用が認められている場合もあります。
ここでは、建設会社が外国人を雇用する方法について説明いたします。
建設会社が雇用することのできる外国人
外国人が日本に在留することのできる資格を、在留資格といいます。
建設会社が、雇用することのできる外国人は、次の在留資格を持つ外国人に限られます。
1.特定技能
2.永住者
3.日本人の配偶者等
4.永住者の配偶者等
5.定住者
6.技能
7.技能実習生
下記に詳細をご説明いたします。
1.特定技能
特定技能という在留資格は、2019年4月に新設された資格です。
建設現場での単純労働が認められていて、最長5年の就労が認められています。
2.永住者
永住者という在留資格とは、その生涯を日本に生活の本拠を置いて過ごすことが認められた外国人です。
永住者の在留資格は、在留期限が無期限となり、日本人と同じようにどのような職業でも就くことができます。
3.日本人の配偶者等
日本人の配偶者等という在留資格には、以下の3つがあります。
① 日本人の配偶者
② 日本人の特別養子
③ 日本人の子として出生したもの
① 日本人の配偶者
日本人と結婚している人です。
しかし、内縁関係は含みません。
② 日本人の特別養子
民法という法律が規定している特別養子です。
普通用紙では、在留資格は認められません。
③ 日本人の子として出生したもの
実子以外でも認知された非嫡出子も含みます。
4.永住者の配偶者等
永住者の配偶者等という在留資格とは、「永住者の配偶者」・「特別永住者の配偶者」・「永住者の子」が該当します。
5.定住者
定住者という在留資格とは、日本での一定の在留期間の居住が認められたものです。
日系3世などが該当しますが、就労に制限がありませんので、建設会社は雇用することができます。
6.技能
技能という在留資格とは、外国の特有の建築に関する技能を必要とする業務に就かせるために、認められた在留資格です。
例えば、建築様式にはゴシック様式など日本にない建築様式もあります。そのような外国特有の建築様式に従事させる場合の資格です。
しかし、外国特有の建築様式の建設現場であっても単純労働では雇用することができません。
7.技能実習生
技能実習生という在留資格とは、開発途上国の人に日本の技術や知識を習得して母国に帰ってから役立ててもらう趣旨の制度です。
ですので、日本の人出不足を補うために単純労働をする労働力として技能実習生制度を利用してはいけないとされています。
外国人技能実習生
ここでは、建設会社が一番活用しているであろう、在留資格技能実習生についてご説明いたします。
建設会社が、外国人技能実習生を雇用するには、建設業許可(金看板)が必要になりました。詳細はこちらをご覧ください。
外国人技能実習生の雇用の仕方
外国人技能実習生を雇用するには、以下の二つの方法があります。
1.企業単独型
2.団体管理型
下記に詳細を説明します。
1.企業単独型
企業単独型とは、主に大企業が技能実習生を雇用する場合です。
企業単独型で外国人技能実習生を雇用する要件は下記のとおりです。
① 送り出しの国の現地法人等の常勤職員
② 引き続き1年以上又は過去1年間に10億円以上の取引実績のある取引先の常勤職員
③ 送り出しの国の公務員等
【企業単独型】
日本の企業等が海外の現地法人・合併企業・取引先の職員を受け入れて雇用する方法

2.団体管理型
団体管理型とは、事業協同組合等の中小企業団体や商工会議所等が、受け入れ団体となって傘下の中小企業で雇用するものです。
【団体管理型】
事業協同組合等の中小企業団体や商工会議所等のの営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で雇用する方法

以下、団体管理型についてご説明します。
在留資格 技能実習生
技能実習は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習1号
技能実習1年目は、技能実習1号となります。
最初の2ヵ月間は、座学で講習を受けます。
この講習期間は、雇用関係にありません。
技能実習1号から次の技能実習2号になるには、学科と実技からなる技能評価試験に合格することが必要です。
技能実習2号
2年目3年目は、技能実習2号になります。
技能実習2号から次の技能実習3号になるには、実技からなる技能評価試験に合格することが必要です。
また、技能実習2号から次の技能実習3号になるには、職種・作業が法令で定められています。
【法令で定められている職種・作業一覧】は、こちらからどうぞ
技能実習3号
4年目5年目は、技能実習3号になります。
技能実習3号を実施できるのは、【優良な実習実施者・監理団体】に限られています。
優良な実習実施者・監理団体
実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に申告書を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に申告書を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。
*「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。
* 団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります。
技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
| 企業単独型 | 団体監理型 | |
|---|---|---|
| 入国1年目 (技能等を修得) |
第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) |
第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
| 入国2・3年目 (技能等に習熟) |
第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) |
第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
| 入国4・5年目 (技能等に熟達) |
第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) |
第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
技能実習生の人数枠
建設会社が雇用できる外国人技能実習生については上限数が定められています。
以下の表のとおりです。
団体監理型の人数枠
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
| 実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | ||||
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
| 201人〜300人 | 15人 | ||||
| 101人〜200人 | 10人 | ||||
| 51人〜100人 | 6人 | ||||
| 41人〜50人 | 5人 | ||||
| 31人〜40人 | 4人 | ||||
| 30人以下 | 3人 | ||||
 お気楽にお問い合わせください。電話 (058)215-5077
お気楽にお問い合わせください。電話 (058)215-5077
建設会社の外国人雇用のご不明点は、岐阜ひまわり事務所までご相談ください
岐阜ひまわり事務所の強み
岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、全ての建設事業、工事施工、業種に対応した許可申請を代行するのはもちろんの事、経営管理責任者、専任技術者の資格要件、実務経験年数などをわかりやすくご説明させていただきます。これは建設業法を熟知したスタッフがいるからできます。また助成金申請も得意としていますので、詳細は助成金のページをご参照ください。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・建設業許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 建設業 助成金申請 介護業 派遣業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077

ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
介護事業コンサルタント
愛知で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で助成金申請代行
岐阜で助成金申請代行
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
愛知で会社設立
岐阜で会社設立
派遣業 独立開業経営支援
愛知で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077






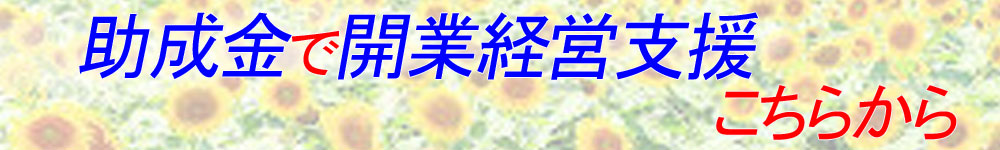















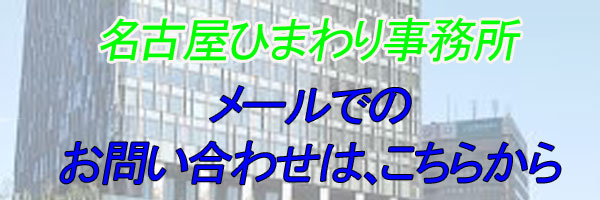


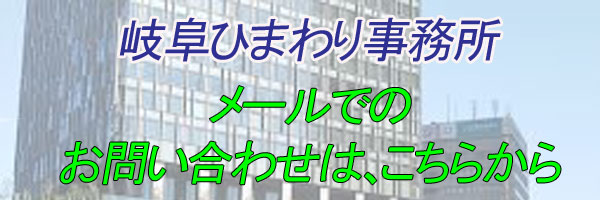














 メールでのお問合せはこちらから
メールでのお問合せはこちらから

